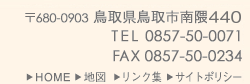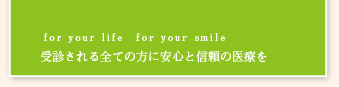膀胱全摘除術に逡巡した“間質性膀胱炎”のはなし “2025年同門会誌から” - 2025年10月5日
膀胱全摘除術に逡巡した“間質性膀胱炎”のはなし
“2025年同門会誌から 追記含む”
私は、今春で医師として36年目を迎えます。医師になった頃の1990年代において、膀胱癌に対する膀胱全摘除術後の5年生存率は約50%程度でしたが、近年では60%から70%に改善しています。しかし、膀胱全摘後の成績が依然として満足なものではない理由の一つには、pT1,G3のような症例(表在癌だが悪性度が高い)において医師が膀胱全摘術を逡巡することも要因ではないかと個人的に思っています(追記:膀胱全摘をすると多くの症例では尿が腹部から出る尿路変更をしなくてはならないからです)。
本稿では、膀胱全摘に対する“医師のためらい”が患者さんに不必要な苦しみをもたらした間質性膀胱炎について述べたいと思います。当院は開業から13年が経過し、これまでに12人の間質性膀胱炎患者(難病指定疾患)を診察しております。開業2年目に訪れた60代の女性患者さんは、強い膀胱痛や1日30回超の頻尿などの症状に悩まされていました。膀胱鏡検査では明らかなハンナ病変や五月雨状出血の所見が認められたため、間質性膀胱炎と診断し治療を開始しました。抗コリン薬、鎮痛剤、抗うつ薬、IPD、リリカなどの内服治療、同疾病治療で有名な県外のクリニックにも紹介し水圧拡張術を計3回施行、当院でも外来水圧拡張術やキシロカインによる膀胱粘膜麻酔を複数回試行しました。約4年間、あらゆる治療法を試みましたが膀胱痛や頻尿は改善されず、患者さんは夜間に1時間おきにトイレに通い、終日の膀胱痛にも耐えていました。患者さんの表情は常に苦渋に満ちており、私自身も医師としての無力感を強く感じていました。
治療選択肢として膀胱全摘除術が挙げられましたが、文献も少なく良性疾患に対するその決断には大きな“ためらい”がありました。数年間にわたり患者さんの苦しみを聞き続ける中で、「膀胱全摘しかないのだろうか」という自問自答が続きました。この症例について、Stanford大学での研究室同窓のY教授(昭和大学)に相談しました。Y教授からは「膀胱拡大術や膀胱全摘の適応はあると思う」との意見をいただきましたが、東京大学のI特任教授にも相談するよう勧められました。患者さんの経過をI教授にもメールで伝えると、「ハンナ型の終末像と思われるので膀胱全摘の適応はある」との意見と膀胱内圧測定と排尿時膀胱造影などの追加検査の指示をいただきました。これを受け、私は患者さんとご家族に教授たちの見解を説明し、膀胱全摘が選択肢となることを伝えました。患者さんは藁をもすがる思いで、その提案を直ぐに受け入れようとしましたが、膀胱全摘による尿路変更についての理解不足が懸念されたため、私は複数回にわたり家族と面談し尿路変更について詳細に説明しました。ここで直面した悩みは、尿道を残して小腸代用の新膀胱を作るか、膀胱・尿道摘除術と回腸導管を選択するかというものでした。文献によれば、尿道を残す場合には膀胱痛や骨盤痛が残存するリスクがあることが報告されています。最終的には、この痛みと完全に決別することを第一と考え、膀胱と尿道の両方を摘出することを選択しました。
I教授からは、「東大で手術してもよいが、膀胱全摘・回腸導管だけなら鳥取で手術されたらどうですか」という助言もいただきました。過日、鳥取赤十字病院の先生の手を借りて膀胱全摘除術・回腸導管増設術は無事に行われ、術後合併症もなく患者さんは退院されました。膀胱尿道全摘後にも痛みが残る症例報告(機能性身体症候群とのoverlap) もあり経過は不安でしたが、退院後の患者さんの表情は見違えるほど明るくなり、難治性間質性膀胱炎に対して膀胱全摘除術を選択して本当に良かったと実感しました。術後6年が経過しましたが、患者さんは年に2回程度の受診を続けており、膀胱全摘後の経過に満足している様子です。患者さんの笑顔を見ると、治療の選択肢に間違いはなかったという確信と、私の決断が遅れたために何年もの間苦しい日々を味わわせてしまったのではないかという後悔を感じます。間質性膀胱炎の病態解明は進んでいますが、依然として未知の部分も多い疾患です。今後の研究成果に期待したいと思います。